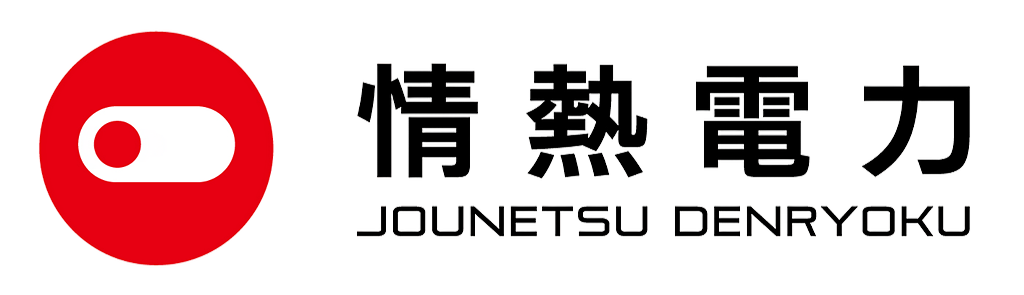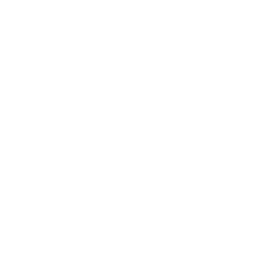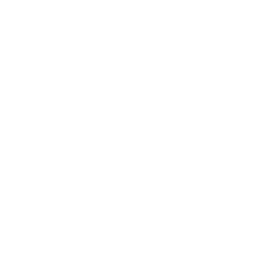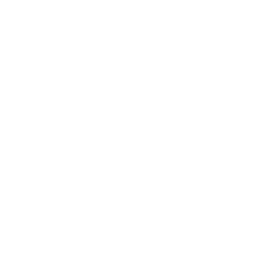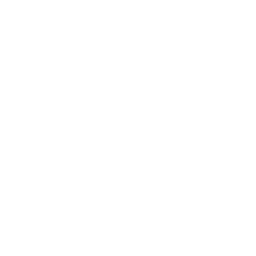再生可能エネルギーのコストは高い?低減に向けた取り組みを解説

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力などの温室効果ガスを発生させないエネルギーです。環境に優しいという理由から導入が促進されていますが、コストの問題から導入に踏み切れない事業者が多くいます。この記事では、再生可能エネルギーの導入コストについて、日本と世界の比較やコスト削減に向けた取り組みなどを紹介します。
この記事を読むための時間:3分
再生可能エネルギーの導入コストについて
再生可能エネルギーの導入コストについて、以下の2つより解説します。
- 日本と世界の比較
- 日本の導入コストが高い理由
日本と世界の比較
日本では、再生可能エネルギーの中でも太陽光発電が最も多く導入されています。しかし、太陽光発電の導入コストを日本と欧州で比較すると、おおよそ2倍程の差があると言われており、日本の導入コストはかなり高いことがわかります。
日本の導入コストが高い理由
日本で再生可能エネルギーの導入コストが高い理由は、以下の2つが考えられます。
- 再生可能エネルギーを導入できる土地が少ない
- 台風や地震などがあり設備の維持や修理にコストがかかる
- 電気工事の費用が高騰している
日本では自然災害が多く、再生可能エネルギーを導入できる土地が少ないです。また、災害が多いと設備を頑丈にする必要があるため、欧州に比べて設置コストがかかると予想されています。
再生可能エネルギーのコスト低減に向けた国の取り組み
再生可能エネルギーのコスト低減に向けた国の取り組みを紹介します。
- FIT制度・FIP制度
- 環境・エネルギー対策資金
- 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
FIT制度・FIP制度
再生可能エネルギーの導入にはコストがかかるため、発電した電力を売電することで導入コストの回収につなげられるFIT制度とFIP制度があります。
FIT制度(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、一定期間一定価格で電力会社が買い取ることを国が約束する制度です。安定的に売電できるため、再生可能エネルギーの導入コスト回収や収益を得られるのがメリットです。
一方FIP制度とは、電気の買取価格が固定されていないため、市場の需要と供給により売電価格が変動します。需要の高い時に売電すると高く買い取りしてもらえるので、FIT制度を利用するよりも高い収益を得られる可能性があるのがメリットです。
環境・エネルギー対策資金
環境・エネルギー対策資金とは、太陽光発電や地熱発電、水力発電、風力発電などの非化石エネルギーの導入をする際に、国から融資を受けられる制度です。返済期間と融資限度額は以下のとおりです。
|
事業区分 |
返済期間 |
融資限度額 |
|
国民生活事業 |
20年以内 |
7,200万円 |
|
中小企業事業 |
20年以内 |
7億2千万円 |
申し込みの際は、日本政策公庫の支店に問い合わせると、融資に関する説明を受けられます。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置とは、再生可能エネルギーの発電設備を設置した際にかかる固定資産税を、課税開始年度から3年分軽減できる制度です。軽減率は再生可能エネルギーの種類によって変わるため、事前に調べると良いでしょう。
再生可能エネルギーのコストを削減する方法
再生可能エネルギーのコストを削減する方法を、2つ紹介します。
- 導入費用を抑えた太陽光パネルを使う
- メンテナンスにロボットやドローンを導入する
- センサーやカメラを使った遠隔監視や異常検知などを導入する
導入費用を抑えた太陽光パネルと使う
太陽光発電のパネル設置には、パネルの購入費用のほかに施工費用がかかるため、導入コストが高くなりやすいです。そこで、従来品に比べて施工が容易な太陽光パネルを導入すると、施工費用を抑えてコスト削減につながります。最近、新たな太陽光パネルも誕生しており、今後、導入費用を抑える取り組みが期待されています。
メンテナンスにロボットを導入する
再生可能エネルギーを導入する場合、設備の定期的なメンテナンスが必要になるため、人件費がかかります。そこで、定期メンテナンスの際にロボットやドローンを導入すると、人件費を抑えられてコストの削減につながります。
再生可能エネルギーのコスト削減は制度を利用しましょう
再生可能エネルギーを導入するにはコストがかかるため、一般家庭はもちろん企業でも導入しにくいのが現状です。しかし、導入コストを削減するために、FIT制度やFIP制度などの取り組みがあるので、制度を活用することでコストを抑えられます。再生可能エネルギーの導入は、制度を利用してコストを削減しましょう。