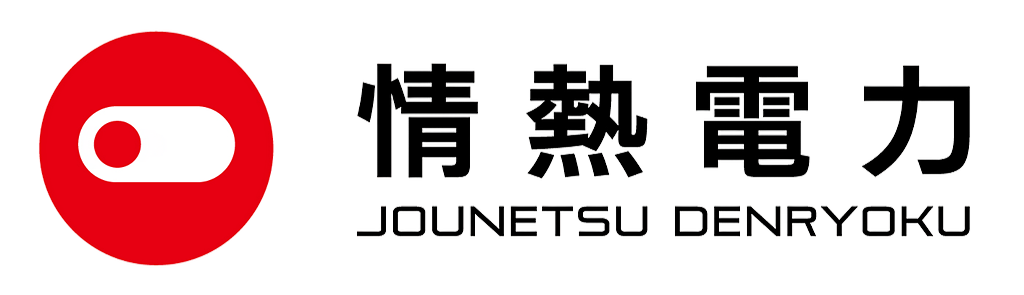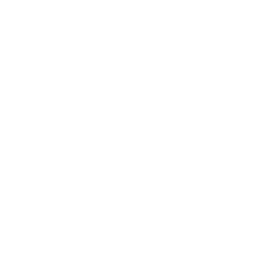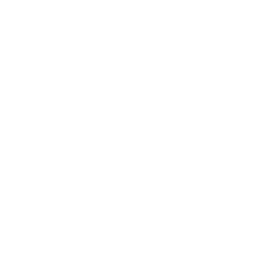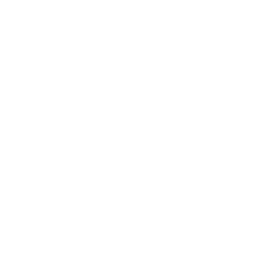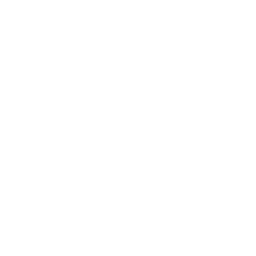![]()
高圧電力と低圧電力を徹底比較!それぞれの定義をわかりやすく解説

現代社会の発展の基盤となっている電力は、低圧電力、高圧電力、特別高圧電力など、いくつかの異なる区分に分類されています。これらの電力はそれぞれ異なる特徴やメリット・デメリットを持っているため、使用する際は適切な契約区分を選択しなければなりません。
本記事では高圧電力と低圧電力に着目し、それぞれの定義や違い、使用される施設について詳しく解説します。各電力の特徴に関しても紹介するので、どの電力プランを契約するか悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
この記事を読むための時間:5分
高圧電力とは
高圧電力は、比較的高めの電圧範囲(直流:750V超から7,000V以下、交流:600V超から7,000V以下)で供給される電力のことを指します。通常6,000Vで供給され、規模が大きいショッピングモールやマンション、病院といった電力消費量が多い施設で使用されています。
ただし高圧電力を直接一般の電気機器に接続することはできないため、供給先の敷地内にキュービクルと呼ばれる受変電設備(鉄の箱のようなもの)を設置して適切な電圧に調整しなければなりません。
高圧電力の使用が適した施設
高圧電力は、以下に示すような多くの電力を必要とする大規模な施設で利用されています。
- 中小規模の工場や製造施設
- ショッピングモール
- オフィスビル
- 病院
- 学校
- マンション
これらの施設では多数の電気機器が常時稼働しており、電力需要が大きく安定した供給が求められるため高圧電力が利用されます。
高圧電力の利点と欠点
高圧電力は、大量の電力を効率的に供給できる点がメリットとして挙げられます。また、安価で購入できるため大量の電力を消費する施設にとってはコスト面でのメリットが大きいです。しかし、電圧を変換するための設備を取り付けなければならないため、初期導入にかかるコストが高額になりやすいです。また、変電設備や電力システムの維持管理のために定期的に費用を支払い続ける必要があります。
さらに高圧電力を扱うには専門的な知識や資格を持った技術者による管理が必要です。大規模な電力需要に応じた効率的かつ経済的な選択肢として高圧電力は適切ですが、その導入には適切な設備と技術者の選任が欠かせません。
低圧電力とは
低圧電力は、低めの電圧(直流:750V以下、交流:600V以下)で供給される電力のことを指します。日本では通常100Vや200Vで供給され、日常生活におけるさまざまな活動に必要な電力を供給します。低圧電力の場合、変圧せずに直接電力機器に供給できるため、変電設備を準備する必要がありません。
低圧電力の使用が適した施設
低圧電力が主に使用される施設には、以下のようなものがあります。
- 一般家庭
- 事務所
- 小規模店舗
これらの施設では、家庭用の家電製品やオフィスのパソコンなど、電力消費が比較的少ない機器が使用されているため、低圧電力で対応できます。
低圧電力の利点と欠点
低圧電力の主なメリットは、導入が容易である点です。送電された電力を直接供給できるため、変圧設備がいらず初期コストを抑えることができます。また電圧が低いため安全性が高く、専門的な知識を持つ電気主任技術者の選任が必要ありません。
しかし低圧電力を使用するにあたっていくつかのデメリットが存在します。電圧が低いため長距離の送電では電力損失が発生しやすく、電力供給が非効率になることがあります。また低圧電力の場合、供給できる電力量に制限があるため、電力消費量が多い施設には向きません。
高圧電力と低圧電力の違いとは?

高圧電力と低圧電力は、その特性や用途において明確な違いがあります。適切な電力契約プランを選択するには、それぞれの違いを理解しておかなければなりません。どちらが適切なプランなのかを見極めるためにも、ここで紹介する違いについて把握しておきましょう。
電圧
高圧電力は通常6,000Vで供給されるのに対し、低圧電力は100Vや200Vなどの低い電圧に変換されて供給されます。この電圧の差が、供給できる電力量や送電の効率、安全面に大きな影響を与えます。たとえば、電圧が高いほど送電時の電力損失が抑えられ、効率的に電力を送ることが可能です。
そのため高圧電力は、オフィスビルやショッピングモールなど大量の電力を安定的に確保しなければならないような施設に向いています。一方で低圧電力は安全性が高いため、日常生活の中で安心して電気を使用するのに適した電力です。
契約電力
高圧電力と低圧電力は、契約する電力の規模にも差がある点が特徴です。契約電力とは、電力会社と需要家が契約する最大使用電力のことです。高圧電力の契約は大規模な電力需要を想定しているため、契約電力が50kWから2,000kWと大きめに設定されています。これに対し、低圧電力は一般家庭や小規模な施設向けであるため、契約電力は50kW未満と小さいです。
電力の供給方法
電力の供給方法の違いについて理解するには、まず発電所から最終需要家までの電力の流れを知ることが重要です。発電所で発電された電力は、効率的に送電するために主に「超高圧電力(特別高圧)」「高圧電力」「低圧電力」の順番で段階的に電圧を変換しながら供給されています。
超高圧電力のように高い電圧で電力を送り始める理由は、送電時のエネルギー損失を最小限に抑えるためです。変電所に到達した電力は、次に高圧電力に変換され、中小規模の工場や学校、ショッピングモールなどに向けて送られます。しかし一般の電気機器に高圧電力を直接使用することはできないため、敷地内に設置された受変電設備によって必要な電圧に調整しなければなりません。
この時点で需要家に送られなかった電力は、さらにいくつかの変電所や柱上変圧器などを経て低圧電力に変換され、一般家庭や小規模店舗に供給されます。低圧電力は、送電網から供給される際にはすでに電圧が低く設定されているため、敷地内に変電設備を設置しなくても問題ありません。
料金
高圧電力と低圧電力の料金体系には、料金単価や契約種類に関する違いがあります。高圧電力の料金単価は、低圧電力よりも安く設定されていることがほとんどです。その原因は、低圧電力で送電する方が変電や送電に関するコストがかかるだけでなく、効率的に大量の電力を供給できないからです。また契約方式にも違いがあり、低圧電力の場合は主に以下の3つのプランの中から選択します。
- 主開閉器契約:ブレーカーの容量によって契約電力を設定する
- 負荷設備契約:設置されている電気機器の合計容量に基づいて契約電力を決定する
- 実量制契約:実際に使用された最大の電力量に基づいて契約電力を決定する
一方で高圧電力には、「実量制契約」の他に電力会社と需要家が協議して契約電力を決定する「協議制契約」があります。協議制契約では、需要家の電力使用パターンに応じた柔軟な契約が可能です。
電線の種類
低圧電力と高圧電力では、使用される電線の種類に違いがあります。低圧電力では、主に家庭や小規模な商業施設で使用される単相2線式や単相3線式の配電方式が使われます。高圧電力の場合、高圧の電力が流れても問題のない三相3線式や三相4線式の電線が主流です。
特徴を理解して、適切な電力プランを見極めよう
本記事では、高圧電力と低圧電力といった2つの電力の種類に注目し、それぞれの定義や違い、使用される施設について詳しく解説しました。高圧電力と低圧電力の違いを理解することで適切な電力プランが見極められます。今回紹介した内容を参考にして、施設の規模や電力消費量、安全性などを総合的に評価したうえで最適な電力プランを選択しましょう。