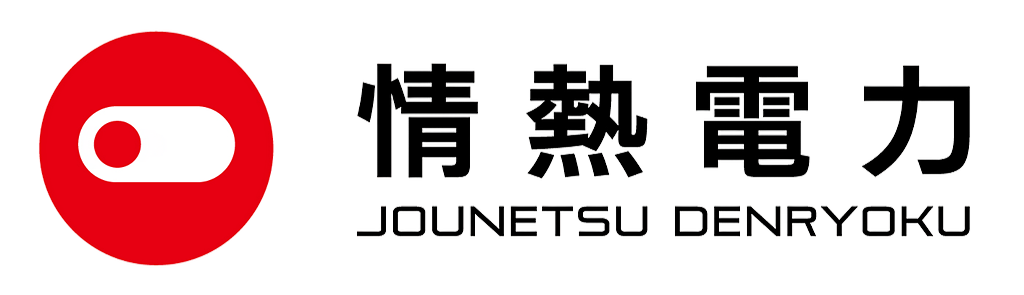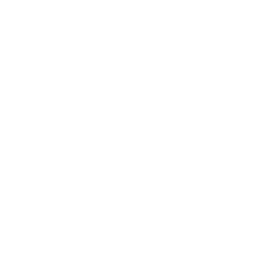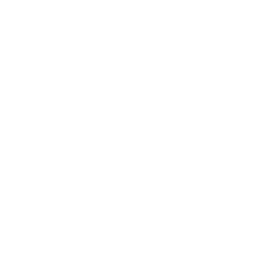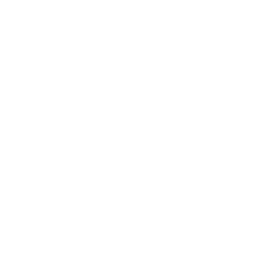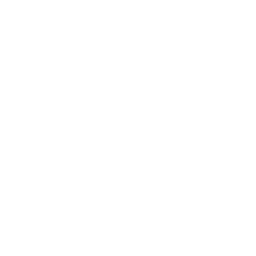![]()
再エネ賦課金とは?再生可能エネルギー発電促進賦課金の仕組みを解説

電気料金を確認すると「再エネ賦課金」という項目があります。毎月支払うものですが、何にかかるお金かわからない人も多いでしょう。そこでこの記事では、再エネ賦課金について、制度の内容や仕組みを解説します。
この記事を読むための時間:3分
再エネ賦課金とは?
再エネ賦課金とは「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略称です。再エネ賦課金は、電力会社が事業者や一般家庭から再生可能エネルギーによって発電した電気を買い取るための賦課金で、基本的に契約している電力会社に毎月支払います。賦課金の内容を知るには、日本における再生可能エネルギーの現状と固定価格取引制度について知る必要があるので解説します。
再生可能エネルギーとは
再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、水力、地熱などの自然由来のエネルギーです。石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料を使用するエネルギーと違い、何度も繰り返し使えて、温室効果ガスを排出しないのが特徴です。
日本の再生可能エネルギーの現状
日本の発電方法では、石油や天然ガスなどを使用する火力発電が約70%を占めており、再生可能エネルギーによる発電は全体の20%程になります。
化石燃料を使用する発電方法を続けると環境に悪いだけでなく、資源の枯渇という問題に直面するため、国としては再生可能エネルギーの割合を増やしていきたい方針です。しかし、太陽光発電や風力発電の設備を導入するにはコストがかかるので、一般家庭や事業者では再生可能エネルギーを取り入れにくいのが課題となっています。
固定価格買取制度について
再生可能エネルギーは導入しにくいという課題を解決するために、2012年から固定価格取引制度(FIT制度)を導入しました。固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーによって発電した電力を、一定期間に一定価格で電力会社が買い取ると国が保証したものです。この制度によって一定期間は安定的に売電できるため、事業者や一般家庭に再生可能エネルギーの導入を進める狙いがあります。
再エネ賦課金の仕組み
再エネ賦課金の仕組みを、以下の2つより解説します。
- お金と電気の流れ
- 賦課金額の計算方法
お金と電気の流れ
再エネ賦課金のお金と電気の流れは、以下のとおりです。
- 再生可能エネルギーにより発電した電力を電力会社に売る
- 電力会社は賦課金を含めた資金で電気を買う
- 電力会社は買い取った電気を一般家庭に提供する
- 電力会社と契約している世帯は再エネ賦課金を支払う
- 電力会社は再エネ賦課金を国に納付する
- 国は電力会社に交付金を支払う
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの発電による電力を、電力会社が買い取る時に使用するため、買い取る電力が多いと賦課金も高くなります。
賦課金額の計算方法
再エネ賦課金の計算方法は、「1ヶ月の電気利用量(kWh)×その年度の再エネ賦課金単価」です。再エネ賦課金単価は年度によって変わり、2024年度は1kWh当たり3.49円になります。1ヶ月の電気利用量を単身世帯の約200kWhで考えると、「1ヶ月の電気利用量200kWh×再エネ賦課金単価3.49円=698円」となり、1ヶ月の再エネ賦課金の合計金額は698円になります。
再エネ賦課金の年間推移
再エネ賦課金の単価は年度によって異なり、経済産業大臣が設定しています。単価は世界情勢などの影響によっても変わりますが、2023年を除いて年々単価は上昇しているのが特徴です。単価が上がると家庭の負担も大きくなるため、今後の価格の推移が注目されています。
再エネ賦課金は制度の内容をよく理解しましょう
再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーによって発電した電気を電力会社が買い取るために使うお金です。日本では再生可能エネルギーによる発電量が少ないため、固定価格買取制度を導入して電力会社が電気を買い取る仕組みを作り、そのための費用として一般世帯から賦課金を徴収しています。再エネ賦課金は制度の仕組みや内容をよく理解しましょう。
電気料金の仕組みについて問い合わせしたい → 株式会社情熱電力